レポート
2025.3.11(火) 公開
リテールテックJAPAN 参加レポート
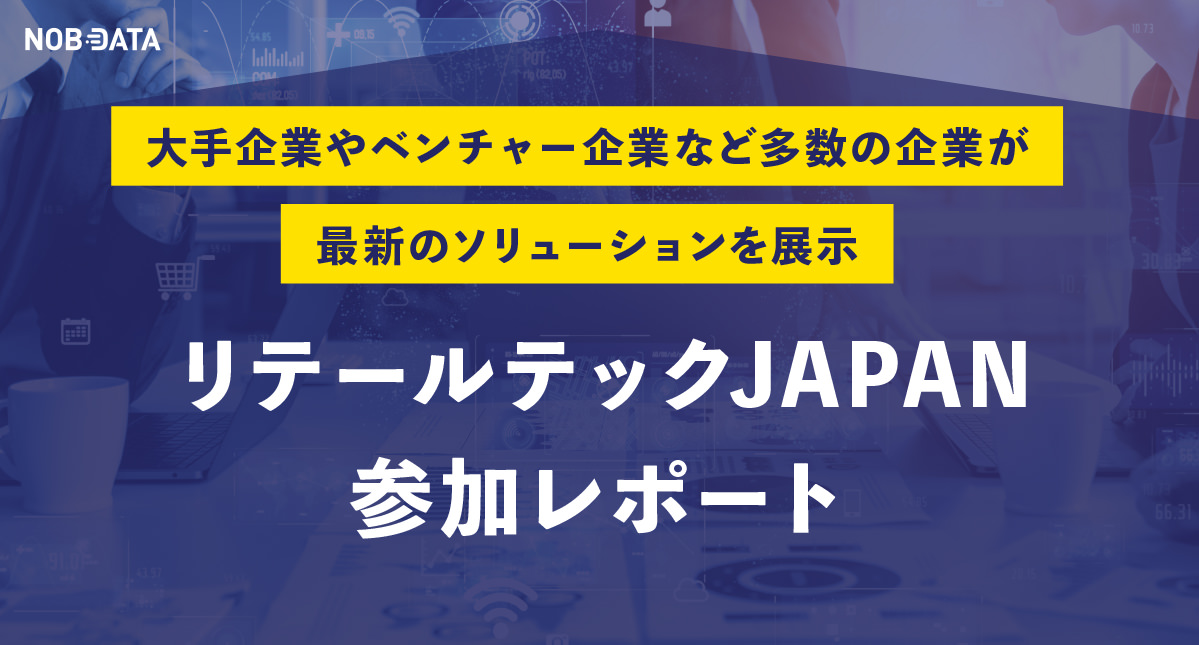
今回は、日本経済新聞社が主催する「リテールテックJAPAN」に参加してきました。

当イベントでは、リテールテックというキーワードのもとで、大手企業やベンチャー企業など多数の企業が、最新のソリューションを展示していました。
レジなどのハードウェアや、EC・デジタルマーケティング、リテールメディア、キャッシュレス決済、流通HRなど、リテールテックといっても、幅広い領域で展示がありました。また、リテールテックに関する様々なテーマで、セミナーやワークショップも開催されていました。
その中で、特にAI・データ活用に関する展示やセミナーについて触れていきたいと思います。
1. セミナー:商品情報の共有化に関する取組について
本セミナーは、日本の流通業における商品情報のデジタル化と標準化の必要性について、経済産業省が取り組む政策を中心に、経済産業省 商務・サービスグループ参事官 中野 剛志 氏が講演しました。
現在、流通業界では消費者の価格抑制圧力が強まる一方で、人手不足や賃上げの必要性が高まっています。そのため、企業は生産性向上を迫られていますが、特に労働集約型の作業が多い業界では、この課題が深刻です。経済産業省は、デジタル化による業務効率化が必要であるとし、流通業の生産性向上に向けた施策を推進しています。
まず業界全体でのデジタル化を進めるために、企業間の協力を求めました。しかし、流通業の産業構造は複雑で、製造業や卸売業と異なるシステムを持っているため、商品情報の管理について、標準化が進みにくい状況がわかりました。そこで、経済産業省は、企業間の共通基盤を作り、情報の統一化を図ることで、業界全体の生産性向上を促す方針を示しました。
具体的には、2026年を目標に、業界全体で共通のデータフォーマットを導入し、商品情報の標準化を進める計画が発表されました。この取り組みでは、消費者に対する説明責任の強化、共通IDの導入、情報の一元管理などを原則として定め、まずは基本項目の統一から始めるとされています。その後、段階的に情報の充実を図り、将来的には商品データの高度な活用を目指します。
このデジタル化の取り組みは、単なる業務効率化にとどまらず、流通業の競争力を高め、データドリブンな経営を可能にする重要なステップとなります。初期段階では限定的な運用となるものの、長期的には業界全体のデータ基盤を整え、さらなる発展を目指す構想が示されました。
2. 展示:リテールDXによる店舗業務の効率化
リテールDXとは、店舗運営の効率化を目的としたデジタルトランスフォーメーション(DX)の一環であり、展示会では多くの企業が関連技術を紹介しておりました。主な技術やソリューションの特徴は、以下のとおりです。
無人店舗・セルフレジの進化
多くの企業が、レジ業務の省人化を促進するためのセルフレジや無人決済システムを展示しておりました。これにより、少ない人員での店舗運営が可能となり、人手不足の解消に貢献することが期待されます。

業務支援AIの導入
AIを活用した在庫管理や需要予測ツールが展示されており、売上データや顧客の行動をリアルタイムで分析することで、適切な発注や価格調整を行う仕組みが提案されておりました。

バックヤード業務の効率化
店舗スタッフの負担を軽減するためのロボットや、自動化された発注・棚卸システムも多数紹介されており、単なる接客支援にとどまらず、店舗の裏方業務の効率化も進められていることが伺えました。
セミナーでも語られた、小売業界が直面している「慢性的な人手不足」という課題に対し、これらのDX技術がいかに貢献できるかが強調されておりました。特に、店舗スタッフの負担を軽減しつつ、業務の効率を向上させる技術の必要性が高まっており、今後の普及が期待されます。
3. 展示:AIとデータ活用による新たな価値提供
リテールDXが「業務効率化」に重点を置く一方で、AIやデータ活用は「新たな顧客体験の創出」という観点から多くの展示が行われておりました。特に印象的だったのは、AWSのブースで紹介されていた以下のソリューションです。
- デジタル百貨店による高級商材の販売
立体ディスプレイと生成AIを活用し、まるで店員が説明しているかのように商品を紹介するシステムが展示されておりました。この技術により、高級品の魅力をよりリアルに伝え、オンラインショッピングでありながら対面販売に近い体験が提供できるようになります。

- 多言語対応の接客AI
インバウンド需要への対応として、AIによる多言語対応の接客システムが紹介されておりました。外国人観光客に対し、音声やディスプレイを通じて商品の説明を行うことが可能であり、言語の壁を超えたスムーズな購買体験を提供できる点が特長です。

これらの技術は、単なる業務効率化にとどまらず、顧客の購買意欲を高める新しい体験価値を提供するものであり、小売業の売上向上にも寄与することが期待されます。
異業種からのリテール参入
また、本展示会では、リテール業界以外の企業が持つ技術やデータを活用し、新たな形で小売業に貢献する動きも目立っておりました。特に興味深かったのは、ナビタイムの取り組みです。
- 住所データの活用による店舗管理の最適化
ナビタイムは、これまで交通・地図情報の分野で培ってきた技術を活かし、小売業や飲食業の店舗データ管理を支援するソリューションを展示しておりました。これにより、商圏分析や出店計画の精度向上、配送ルートの最適化など、小売業にとって非常に有用なデータ活用が可能となります。

このように、異業種の技術がリテール業に活用されるケースは今後さらに増加することが見込まれ、業界を超えたコラボレーションのさらなる進展が期待されます。
4. まとめ
長年リテール領域のAI・データ活用に携わってきた立場から、「リテールテックJAPAN」に参加し、改めて業界の進化を肌で感じました。特に、データ標準化の取り組みや、AIを活用した業務効率化・顧客体験の向上が着実に進んでいる点が印象的でした。
セミナーでは、業界全体の生産性向上に向けたデータ標準化の重要性が強調され、今後の課題と方向性が明確になりました。流通業のデジタル化は避けて通れない道であり、官民連携による取り組みがさらに加速することを期待したいと思います。
展示会では、無人店舗や業務支援AIなど、省人化と業務効率化に向けた技術が多く紹介され、小売業の現場における変革のスピードを感じました。一方で、AIによる新たな価値創出も進んでおり、デジタル百貨店や多言語対応の接客AIなど、顧客体験の向上に寄与する技術が増えている点も興味深かったです。
また、ナビタイムのように異業種からの参入が増え、データ活用の幅が広がっているのも印象的でした。リテール業界の発展には、業界内のイノベーションだけでなく、異業種との連携が重要であることを再認識しました。
全体として、AI・データ活用の進化がリテール業界における大きな変革を促していることを実感できるイベントでした。今後も、業界全体でデータ活用の取り組みが進み、より効率的かつ顧客に価値を提供できるエコシステムが築かれていくことを期待しています。
この記事の著者
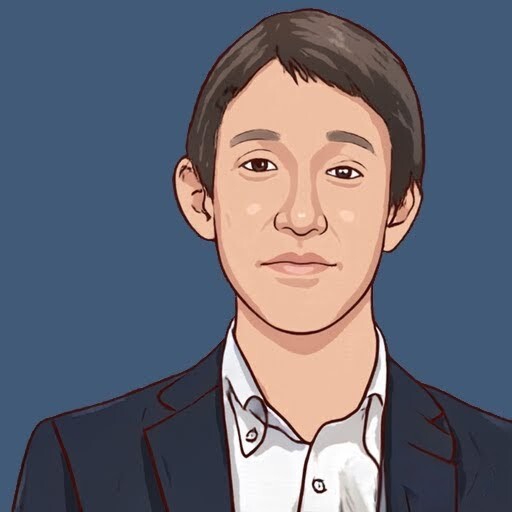
データサイエンティスト
烏谷 正彦
AI系のスタートアップ企業で、データサイエンティストとしてビッグデータを用いたアナリティクスを提供。現在は、生成AIのソリューションや教育を提供するフリーランスとして活動。最近の趣味は、銭湯に向けてランニングをすること。NOB DATAでは、生成AIまわりのリサーチや情報発信を担当。
関連サービス

