レポート
2025.06.18(水) 公開
DX&AI Forum 東京 2025 Spring 参加レポート

今回は、SBクリエイティブ株式会社が主催する「DX&AI Forum 東京 2025 Spring」に参加してきました。
DX&AI Forum 東京 2025 Springでは、3つのトラックに分かれて、様々な分野の方からの講演がありました。今回は、基調講演・企業講演から1つずつ印象に残ったものをまとめていくとともに、全体から感じたDXやAIの未来について述べていきます。
目次
1. 生成AIが導く新たな現場力
東京大学大学院工学系研究科 教授
東京大学 インクルーシブ工学連携研究機構 機構長
川原 圭博 氏
a. はじめに
東京大学大学院の川原教授が、生成AIの最新動向と、それが現場の業務にもたらす革新について講演しました。ChatGPTをはじめとする生成AIの登場は、単なるツールの域を超え、人間の業務の一部を代替・補完する存在として注目を集めています。
b. 生成AIの進化
従来のAIはルールベースで動いていましたが、現在の生成AIは、大量のデータからパターンを学習し、自ら文章や画像を「創造」できるようになっています。特に近年注目されているのが「マルチモーダルAI」です。これは言語だけでなく、画像・音声など複数の情報を統合して処理できるAIであり、より人間に近い理解力を持ち始めています。
また、AIは単なる対話ツールを超えて「AIエージェント」へと進化しています。AIエージェントとは、ユーザーの指示に基づいてブラウザを操作したり、予約をしたりするなど、実行力を持ったAIのことです。こうした機能によって、AIは「考えて答える」だけでなく、「行動する」段階に入りつつあります。
c. 技術的な背景
生成AIの根幹にあるのは、大規模なニューラルネットワークと、インターネット上の膨大なデータです。特に重要なのが「埋め込み技術(embedding)」と呼ばれるもので、これは単語や概念の意味を数学的に数値ベクトルとして表現する方法です。
この技術を使うことで、AIは単語同士の関係性や意味の近さを計算しながら、自然で文脈に沿った文章を生成することができます。たとえば、「王(king)- 男性(man)+ 女性(woman)」=「女王(queen)」といったように、意味の変換まで可能になっています。
d. 現場での応用と課題
生成AIの進化は、製造業や流通業など「現場」の業務にも活用が広がっています。講演では、ロボットが工場や店舗内を自律的に移動し、棚卸しや在庫確認を行う事例が紹介されました。これは「ビジョン・ランゲージ・アクション(VLA)モデル」と呼ばれる仕組みにより実現されています。
具体的には、カメラ映像から対象物を認識し、ユーザーの音声指示に従ってロボットアームが動作を行うなど、視覚・言語・運動を統合した動作が可能になっているのです。このような技術は、従来のようにプログラミングで1つひとつの操作を事前に定義しなくても、柔軟に対応できる点が特徴です。
一方で、課題も残されています。生成AIは「もっともらしい誤情報」を自信をもって出力してしまう「ハルシネーション」や、学習データの偏りによる「バイアス」などの問題があります。こうした問題への対処法として注目されているのが「RAG(Retrieval-Augmented Generation)」という技術です。
RAGでは、信頼性の高い社内文書やナレッジベースなどを検索し、それを基にAIが回答を構成することで、正確さを向上させる仕組みになっています。
e. おわりに
講演の最後に、川原教授は「AIは人の仕事を奪う存在ではなく、現場のパートナーとして共に働く存在である」と述べられていました。生成AIは今後、単なる効率化の手段を超えて、判断力や行動力を備えた現場の支援者となっていくでしょう。
企業にとっては、AIを導入すること自体が目的なのではなく、AIを活用してどのように現場力を強化し、どのような価値を生み出すかが問われる時代になっています。生成AIの可能性を正しく理解し、現場の課題に即した形で導入・活用していくことが、今後の競争力を左右すると言えるでしょう。
2. 次世代DXリーダーの育成:実践で活躍人材を育てる『リスキリング』
パーソルイノベーション株式会社
Reskilling Camp Company 代表
柿内 秀賢 氏
a. はじめに
パーソルイノベーションの柿内氏が、AI時代における雇用や人材育成の課題、そして企業が取るべきリスキリング戦略について講演しました。従来の採用・配置のあり方が変化しつつある中で、社内で人材を育てていく必要性や、スキル可視化から配置・評価までを含む人材育成の全体像について、豊富な事例を交えて解説されました。
b. 雇用の前提が変わる時代背景
かつては経済成長に比例して雇用が拡大していましたが、現在はAIや自動化技術の発展により、その構造が大きく変わっています。アメリカではコロナ後にGDPが回復しても雇用が伸びず、生成AIが事務処理や問い合わせ対応を代替する時代が始まっています。
日本でも、離職率を上回る入職率が続いており、企業は採用した人材を手放さずに育成する方向へと舵を切っています。一方で「採用自体が難しい」「辞めさせることも難しい」という状況に直面しており、今後は育成が企業の成長に欠かせない手段となっていきます。
c. リスキリング戦略の重要性と実践ステップ
人材育成は単発の研修ではなく、スキルの可視化、育成、配置、活躍、評価という一連の流れを回す仕組みが重要です。講演では、AT&T社が10億ドルを投資して10万人を対象にスキル変革を行った事例が紹介されました。このように、リスキリングは企業の事業変革や雇用維持を支える戦略的な投資と位置づけられます。
日本企業においても、次の4段階のステップでリスキリングを進めている事例が増えています。
-
啓発・導入段階:未来に必要なスキルを定義し、育成の土台をつくる
-
実ビジネスとの接続:育成した人材を実際の業務で活かし成果を追求する
-
職種転換を伴う育成:人事異動や業務転換を前提にしたスキル移行を行う
-
人事制度との連動:昇進要件にデジタルリテラシーを組み込むなど制度設計を進める
d. 企業事例:トヨタ・電機メーカーの取り組み
トヨタ自動車では、現場改善とデジタル活用を組み合わせた取り組みが実施されました。ITスキルの高低に関係なく、全社員がDX人材として自らの業務改善に取り組み、チーム単位でスキルを学び、成功体験を共有する文化が醸成されています。
また、ある電機メーカーでは、サイバーセキュリティやAIに対応するため、社内異動によって人材を補い、集中的なトレーニングを実施しています。数ヶ月の学習期間を経てから本配属を行い、専門知識を社内で内製化することで持続可能な体制を築いています。
e. おわりに
AI時代に求められるのは、AIを単に使うリテラシーではなく、「どの業務にどのツールを使うか」を判断し、実装までつなげる力です。講演ではこの能力を「AI共創スキル」と呼び、次の2つの力が重要とされました。
-
業務を構造的に捉え、AIと人の役割を切り分ける力
-
RPAやBIツール、生成AIなどを適切に選び活用する力
このスキルを社内に広げていくことが、競争力の源泉になると強調されました。
AIの発展は企業の雇用と人材戦略を根本から変えつつあります。採用一辺倒ではもはや対応できず、社内人材のリスキリングこそが変化に強い組織をつくる鍵となります。本講演では、「人を育てて戦力化する」という視点を、構造的かつ実践的に示していただきました。
パーソルグループのような人材支援企業が、リスキリング支援や組織変革のパートナーとしてどのような役割を果たしていくのか、今後の展開が非常に注目されます。
3. まとめ:今後のDXとAIの展望
それ以外の講演でも、購買領域や営業領域、マーケティング領域など、様々な実際に生成AI・AIエージェントを用いる事例が多く話され注目を集めていました。
従来のAIは主に情報提供や検索といった受動的な役割にとどまっていましたが、現在のAIエージェントは、自ら考え、行動し、業務を遂行するという能動的な側面を持ち始めています。資料作成やメールの添削、法令遵守チェック、営業戦略の立案支援など、さまざまな分野で実用化が進み、現場の生産性を大きく向上させています。
企業においては、特定の業務プロセスに部分的にAIエージェントを導入する例が多く見られます。すべてのプロセスを一度に自動化するのは現実的ではないため、ルールベースで判断しやすい領域や、繰り返しの多い作業から導入が進んでいます。たとえば、購買や決済におけるコンプライアンス確認や、マーケティングメールの文面チェックなどが挙げられます。
また、営業分野では、顧客との会話ややり取りを自動でキャプチャし、構造化データとして蓄積する仕組みが登場しています。こうしたデータは、そのままCRMやSFAに連携され、次回提案の方針策定やメールの下書き作成などに活用されます。結果として、営業担当者は資料作成や情報収集にかける時間を大幅に削減でき、より付加価値の高い業務に集中できるようになります。
一方で、AI導入にあたっては多くの課題も指摘されています。業務フローの複雑さ、社内データの分散、そしてセキュリティやガバナンスへの懸念などがあり、特に自社でAIを内製化しようとした場合、膨大なコストと専門人材の確保がネックとなります。実際に、AIのPoC(実証実験)に取り組んでも、本番運用に至らずに中断されるケースが少なくないことも明らかになっています。
こうした現状を踏まえると、今後は人とAIがどのように役割を分担し、共に働くかという視点が重要になっていきます。AIエージェントに任せられる範囲は少しずつ広がっていきますが、最終的な判断や確認は人が担い、AIはその支援に徹するという形が、当面は現実的な共存のあり方といえます。また、導入の初期段階では、一気に変革を目指すのではなく、小さく始めて成果を確認しながら拡大していくアプローチが効果的です。
AIエージェントは、単なる効率化のツールではなく、組織の思考と行動の質を高めるためのパートナーになりつつあります。今後のDX推進においては、AIがどのように人の知見を補完し、ビジネスインパクトを最大化できるかを見極めることが、企業の競争優位性を左右する重要なポイントになると考えます。
2025年はAIエージェント元年と言われるほど注目を集めていますが、今回の講演でも本当に様々な分野で注目されていることを実感しました。
その多くが、実践的であり、すぐにでも自分たちの業務に応用ができそうというものが多くありました。
NOB DATAでは、これまでも様々な企業に生成AIに関するシステムや、サービスを導入してきました。
生成AIを導入することでクライアント企業様の成長を促していければと思いますので、これからもツールやサービスについてより学びを深めていき、より良い生成AIに関するシステム・サービスを提供いたします。
この記事の著者
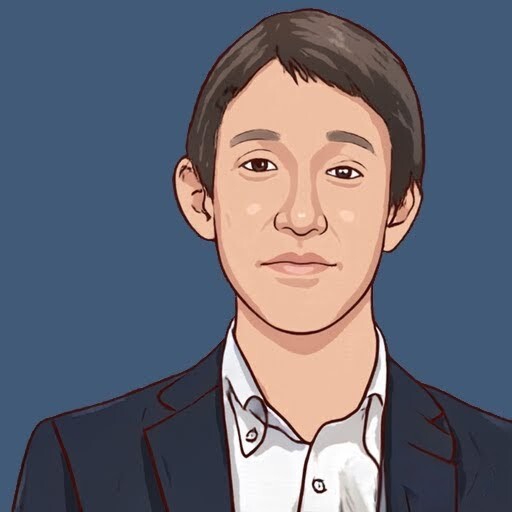
データサイエンティスト
烏谷 正彦
AI系のスタートアップ企業で、データサイエンティストとしてビッグデータを用いたアナリティクスを提供。現在は、生成AIのソリューションや教育を提供するフリーランスとして活動。最近の趣味は、銭湯に向けてランニングをすること。NOB DATAでは、生成AIまわりのリサーチや情報発信を担当。
関連サービス

